【プロが解説】車のサブスクはデメリットだらけ?7つの解決策や利用するメリット、よくある質問まで徹底解説!
- オート KST
- 2023年11月25日
- 読了時間: 13分
更新日:2024年10月25日

「車のサブスクって利用しても大丈夫?」このように感じる方は少なくありません。実際に何も考えずに利用してしまうと、後悔してしまうことも考えられます。
この記事では、車のサブスクサービスのデメリットやその解決策、よくある質問について詳しく解説します。これから車を利用しようと検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
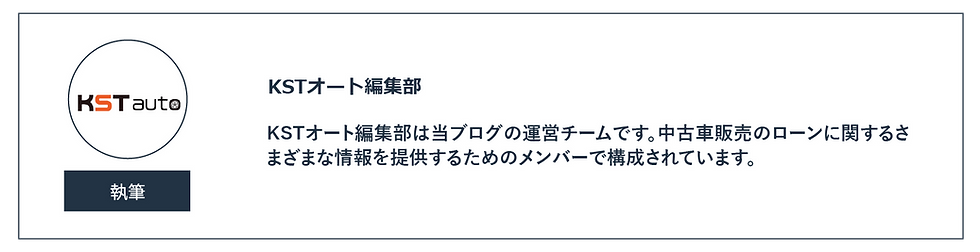
車のサブスクにおける7つのデメリット

車のサブスクにおけるデメリットには、以下の7つが挙げられます。
|
ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.走行距離に制限がある
車のサブスクでは、一般的に走行距離に制限があるためこの点はデメリットです。
万が一制限距離を超えると、追加料金を支払う必要があります。特に通勤やプライベートで長距離を走る方は、この制限をデメリットに感じるかもしれません。
車の劣化を防ぐため、ほとんどのサービスで走行距離に制限を設けており、超過すると返却時に高い費用がかかります。
2.中途解約ができない
車のサブスクでは、中途解約は基本的にできません。万が一、特別な事情で解約が認められた場合でも、違約金が請求されることがほとんどです。この点がデメリットと捉えられることがあります。
購入した車なら、不要になれば売却や廃車の手続きをすれば済みますが、サブスクの場合は、違約金を支払うか、車を利用しなくても契約満了まで料金を支払う必要があります。不必要な中途解約を避けるため、契約期間の選択は慎重にすることが大切です。
3.自由にカスタマイズできない
車のサブスクでは、マイカーのような自由なカスタマイズが原則できません。元に戻せないようなカスタマイズやドレスアップは不可で、車の返却時には原状回復の義務があります。
元に戻せるカスタマイズは可能ですが、追加費用がかかることもあります。この制限は、サブスクの契約終了時に車を返却することを前提としているためです。
4.原状回復費用を請求されるケースがある
原状回復の義務があるため、追加費用が発生することがあります。そのため、傷やへこみ、故障が生じた場合にも、原状回復費用が必要になることがあります。
通常の使用で生じる小さな傷についての心配はいりませんが、運転に不慣れな方や狭い道を頻繁に運転する方は、原状回復の義務をデメリットと感じるかもしれません。
5.残価精算のリスクがある
車のサブスクでは、「残価」という重要な概念があります。
これは契約満了時の車の想定下取り価格のことで、契約時に残価を設定し、車両本体価格からこの残価を差し引いた上で月額料金が算出されます。これにより、車を購入する場合と比べ、残価の分だけ料金が安くなります。
しかし、契約満了時に実際の車の価値が想定下取り価格を下回ると、差額が請求されることがあります。差額が出た場合、予定よりも支払総額が増えることがあり、これはサブスクのデメリットとなるおそれがあります。
6.契約満了時に車を返却する必要がある
車のサブスクでは、利用者は車を一定期間借りて使用することになります。そのため、契約満了時には車を基本的に返却しなければならず、カスタマイズも自由にはできません。
この点は、購入した車のように気兼ねなく使いたい方にとっては、大きなデメリットだと感じられるかもしれません。
7.購入より割高になる場合がある
車をローンで購入する場合の支払総額は、車両本体価格に利息が含まれます。対して、車のサブスクでは、支払総額に残価を差し引いたぶんの車両本体価格に加え、あらゆる費用が含まれます。
これにより、車種や契約内容によっては、サブスクの支払総額が購入する場合を上回ることもあります。しかし、車を購入する際には、税金や保険料、その他の諸費用も別途支払う必要があります。
したがって、ローン購入とサブスクのどちらが最終的に総額が高くなるかは、これら諸費用の総合計を考慮してみないと判断が難しいかもしれません。車を手に入れる方法を選ぶ際は、これらの費用を含めた総コストを検討することが重要です。
デメリットを解決する7つの方法

デメリットを解決する方法には、以下の7つが挙げられます。
|
ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.走行距離制限なしのプランを検討する
車のサブスクサービスの多くは、1ヶ月あたりの走行距離上限を1,000kmから1,500km程度に設定しています。
日本自動車工業会の調査とソニー損害保険株式会社の「2021 全国カーライフ実態調査」によると、乗用車ユーザーの約9割が1ヶ月あたり1,200km以下、または年間11,000km(月換算約916km)以下の走行距離です。
これらのデータから、上限が1,500km程度のサブスクであれば、ほとんどのユーザーにとって十分な走行距離の余裕があるといえます。ただし、毎日運転する場合や長距離ドライブが多い方は、走行距離の上限を超える不安があるため、より余裕ある上限を設定可能なサブスクを選ぶようにしてみてください。
2.違約金のリスクに備えておく
車のサブスクを利用する際、中途解約のリスクへの備えには、任意保険への加入がおすすめです。特に「車両保険」を付帯することで、自損事故や浸水、盗難などによる車両の破損時の補償を受けられます。
さらに、リースカー車両の費用に関する特約が付帯できる保険なら、全損事故による中途解約の際にも解約金が補償されます。
加えて、中途解約リスクを軽減するためには、契約年数を慎重に考えることも重要です。転勤や家族構成の変化など、ライフスタイルの変化を考慮し、自身の生活に合った契約期間を選ぶようにしてみてください。
ほとんどのサービスでは契約期間を3年、5年、7年などから選べ、中には1年単位で選べるものもあります。
3.オプションの選択肢が多い車を選ぶ
一般的に車のサブスクでは、契約満了した際に車を原状回復して返却するのが基本です。しかし、契約満了時にそのまま車を自分のものにできるオプションやプランを提供するサービスもあります。
このようなプランを利用することで、車の返却が不要になり、原状回復も必要なくなります。さらに、マイカーとしてのカスタマイズも自由自在です。
ただし、車をもらえるオプションやプランには、条件や料金が各サブスクサービスによって異なるため、自分にとってお得な条件でマイカーを取得できるサービスを選ぶ必要があります。
4.原状回復費用をカバーできるプランを選ぶ
車のサブスクでは、契約するプラン内容によって原状回復費用の補償を受けられる場合があります。通常の使用で生じる微細な傷ならば追加費用は発生せず、問題ありません。
しかし、大きな傷や凹みがある状態で返却すると、原状回復費用が請求されることがあります。このリスクを避けるためには、傷や凹みを早めに修理することが重要です。
また、メンテナンス費用や車検が月額料金に含まれるメンテナンスプランを選ぶこともおすすめします。ただし、プランやサブスクの内容によって保証は異なり、原状回復費用をカバーするプランはまだまだ少ない傾向です。
5.残価精算不要の契約プランを選ぶ
車のサブスクには「オープンエンド方式」と「クローズドエンド方式」の二つの契約方式があります。オープンエンド方式では、契約満了時に残価精算が発生する可能性がありますが、クローズドエンド方式ではそのような残価精算は発生しません。
残価精算が不安な場合は、クローズドエンド方式を採用している車のサブスクを選ぶことがおすすめです。この方式では、月額料金はオープンエンド方式よりも高めに設定される傾向がありますが、追加請求される心配がないため、契約満了まで安心して利用できます。
6.車がもらえるプランを検討する
車がもらえるオプションを適用できる車のサブスクでは、契約満了時に車を返却する必要がなく、そのまま自分のマイカーとして乗り続けられます。
初期費用が0円で新車に乗り始められ、契約満了まで月々定額の支払いで済みます。契約終了後は、車を自分の資産として持ち続けることも、下取りに出して次の車への乗り換え資金にすることも可能です。
加えて、国産車の全車種全グレードを取り扱う車のサブスクなら、購入時と同等の幅広い選択肢から理想の車を選ぶ楽しみがあります。月々の決まった定額料金だけで最新車種に乗りながら、最終的にはマイカーを手に入れることが可能です。
7.保険料や維持費なども含めた総費用を比較する
車のサブスクの料金体系は、車両本体価格から残価を差し引いた金額に契約期間分の各種税金や自賠責保険料などが上乗せされるため、購入よりも総費用が割高に見えるかもしれません。しかし、購入とサブスクを比較する際は、条件をきちんと揃えて比較することが重要です。
購入する場合、購入費用の他に税金や保険料(自賠責保険、任意保険)、諸費用(車検やメンテナンス費用など)も総費用に含め、車を使用する期間で比較すれば、どちらがより出費を抑えられるかが明確になります。
また、サブスクの利用料金には任意保険が含まれる場合もあり、これにより自分で保険会社を探したり加入手続きをする手間が省けます。さらに、団体契約や保険の契約期間が長期であれば、期間中に保険を使っても保険料が変動しないこともメリットです。
車のサブスクを利用する4つのメリット

車のサブスクを利用するメリットには、以下の4つが挙げられます。
|
ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.初期費用を抑えられる
車を購入する際には、頭金や登録諸費用など、初期にまとまった資金が必要となります。これはローンを組む場合でも同様で、購入時に各種税金や自賠責保険料などの初期費用がかかり、特に新車の場合、中古車と比べて高額になりがちです。
これに対し、車のサブスクは初期費用が不要であり、購入時の諸費用も含めた総額を契約月数で分割した月額定額制を採用しています。そのため、頭金も不要で、貯金が少なくても新車にすぐに乗り始められるのが大きな魅力です。
特に新車の場合、サブスクを利用することで、高い初期費用による負担を減らすメリットを感じやすくなります。
2.諸費用が月額料金に含まれている
車のサブスクの月額料金には、車両本体価格やオプション価格、各種税金、自賠責保険料、登録諸費用、納車費用など、クルマに関する諸費用がすべて含まれています。これにより、税金や自賠責保険料を別途支払う必要がなく、月々の支払いもずっと定額です。
さらに、車検や故障に伴うメンテナンス費用なども定額化できるプランやオプションを利用することで、車の維持費のほとんどを月額料金に組み込めます。これにより、家計管理が楽になり、将来的な予算を組みやすくなることはメリットです。
3.短期間で新車の乗換えができる
車のサブスクは、常に最新モデルの車に乗りたい方に最適な選択肢です。1年や2年の短期契約が可能なサービス会社もあり、契約満了後は車を返却するだけで、簡単に次の新車に乗り換えられます。
契約期間は通常、車検の時期に合わせて3年、5年、7年と設定されており、例えば3年のサブスクを選べば、3年ごとに最新モデルの車に乗り換えることが可能です。
一方、車を購入する場合は、乗り換えのたびに下取りや廃車の手続き、新しい車の購入といった手間が発生します。しかし、車のサブスクでは、売却などの面倒な手間を省き、いつでも最新機能を搭載した新型車に乗り続けられます。
4.多くの車種から選べる
車のサブスクは、多くの場合、複数のメーカーの車種を取り扱っており、選択肢の幅が広い点が特長です。
新車をディーラーで購入する場合は、そのディーラーが扱うメーカーの車種からしか選べませんが、車のサブスクなら、国産メーカーの全車種・全グレードを取り扱っている会社もあり、オプションも自由に選べます。これにより、予算や希望条件に合わせた車選びが可能です。
また、レンタカーやカーシェアリングも車に乗る選択肢のひとつですが、取り扱う車種は限定的で、車選びの自由度が低いというデメリットがあります。対して車のサブスクは、さまざまな車種を提供しており、ライフスタイルに合わせて複数の車種から選べることは大きなメリットです。
車のサブスク デメリットでよくある3つの質問

車のサブスク デメリットでよくある質問には、以下の3つが挙げられます。
|
ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
質問1.そもそも車のサブスクとは?
車のサブスクリプションは、毎月定額で車を利用できるサービスです。これは実際に車を購入するのではなく、利用したい期間分だけ毎月定額の料金を支払って、その期間中車を借りて使用します。
このサービスはカーリース(オートリース)に似ており、契約期間中の各種税金や自賠責保険料、車検基本料なども毎月の料金に含まれているため、車を利用している間の出費を均等にすることが可能です。
また、各自動車メーカーが提供するサブスクリプションサービスはさまざまで、例えばトヨタは「KINTO」というサービス名で車のサブスクリプションサービスを提供しています。このようなサービスは、車の所有に伴う負担を減らしつつ、最新の車を手軽に楽しめることがメリットです。
質問2.車のサブスクとカーリースはどう違うの?
「車のサブスク」と「カーリース」は機能面で非常に似ており、月々定額の料金で好きな車に乗れる点が共通しています。しかし、一般的なサブスクリプションサービスの特徴である「いつでも解約」ができない点が、これらのサービスの大きな違いであり、カーリースの主なデメリットのひとつでもあります。
このデメリットを克服したのが、オリックスのマイカーリース「いまのり」シリーズです。
このプランは、契約開始から一定の期間が経過した後にいつでも解約して車を返却できる特徴を持ち、中途解約金が発生しない点が大きな魅力です。ただし、車両返却時の損耗状態や走行距離によって追加請求が発生する可能性はあります。
質問3.車のサブスクに向いている人は?
車のサブスクに向いている人は、以下のような考え方の人です。
|
車のサブスクリプションは、初期費用や頭金が不要で、月額料金のみで車を利用できるサービスです。この月額料金には自動車税、重量税、保険料などが含まれているため、車に関する出費を毎月一定に保てます。
また、契約期間中でも別の車に乗り換えられるプランがあり、好みの車を柔軟に選べることもメリットです。
まとめ

車のサブスクのデメリットに関することを解説しました。車のサブスクサービスは、デメリットを多く感じてしまいがちですが、事前に購入やカーリースなどほかの方法と比較することで活用できるようになります。
デメリットを解決する方法についても解説しましたので、ぜひこの記事を参考に最適な車の乗り方を見つけてみてください。
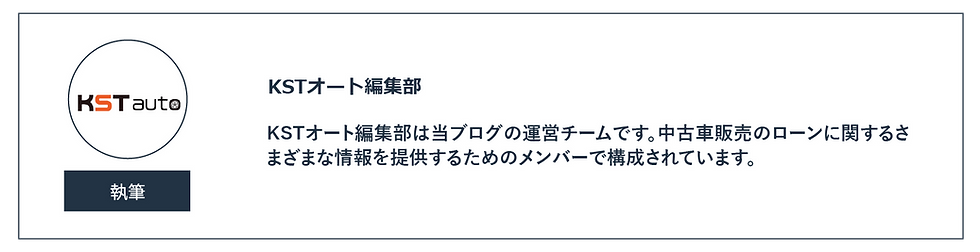





コメント